宅建の改正点を考えながら学ぶ
宅建は改正点が狙われる
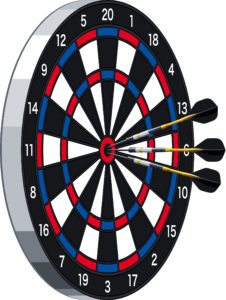
宅建はその年度の改正点が出題されやすいのですが、過去問では取り扱いがありません(当たり前の話ですが)。
そこで今年度狙われるであろう宅建の改正点についての一問一答を作りました。
ただ単に改正点の説明をしても「ふ~~~ん」で過ぎ去ってしまうかもしれませんので、考えられるような設定にしております。
これから紹介する文は全て誤りが含まれています。
どの部分が、どのように間違っているかを答えられれば、正確な知識が身についている状態だと思いますので、そのようにご活用ください。
改正点①
自筆証書遺言の作成方法

自筆証書によって遺言をする場合、その遺言書に添付する目録を含め、その全文を自書しなければならない。
さあ、この問題文ですが何が間違っているか分かりますでしょうか?
2019年の改正点を把握されている方であれば、楽に解ける問題です。
さあ、いかがでしょうか?
正解は・・・
自筆証書によって遺言をする場合、その遺言書に添付する目録を含め、その全文を自書しなければならない。
赤字の部分が間違っています。
昔はまさにこの通りで、財産がある場合は全部手書きをする必要がありました。
財産が多い場合は、かなり負担がかかる事が分かります。
そのため平成30年の民法改正により、新たに以下の規定が新設されました。
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
言葉は難しいのですが、要するに財産目録については手書きでなくてもいい!という事です。
よって以下のような選択肢は全て正解です。
遺言者は、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合にはその目録については自書する事を要しないが、この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
自筆証書によって遺言するには、遺言者がその全文・日付及び氏名を自書し、これに印を押す必要があるが、筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合にはその目録については自書する事を要しない
ちなみに相続はほぼ毎年出題されています。
しかもこの3年は遺言以外から出題されていますので、今年は遺言に関する問題は超要注意です。
改正点②
接道義務の例外

それでは次の問題です。
その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めても、建築審査会の同意がないものは建築できない。
さあ、この問題文ですが何が間違っているか分かりますでしょうか?
これも今年の改正点を把握されている方であれば、楽に解ける問題です。
さあ、いかがでしょうか?
正解は・・・
その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めても、建築審査会の同意がないものは建築できない。
赤字の部分が間違っています。
今年から建築基準法が改正され、以下のようになりました。
その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
と建築審査会が登場していない!というのがポイントなのですが、この論点を理解するためには、そもそも接道とはなんぞや?という所から理解する必要があります。
道路とは?道とは?
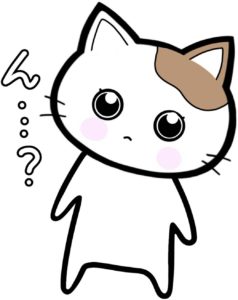
宅建士として重要事項説明をすると良く分かるのですが、接道というのは不動産の実務においては超・重要です。
そして道路と道とは意味が全く違います。
詳細な説明は省きますが、建築物の敷地とは道路に2メートル以上接している必要があります。
これを接道義務と言います。
道路と道の違い(道に接していても建築できない!)
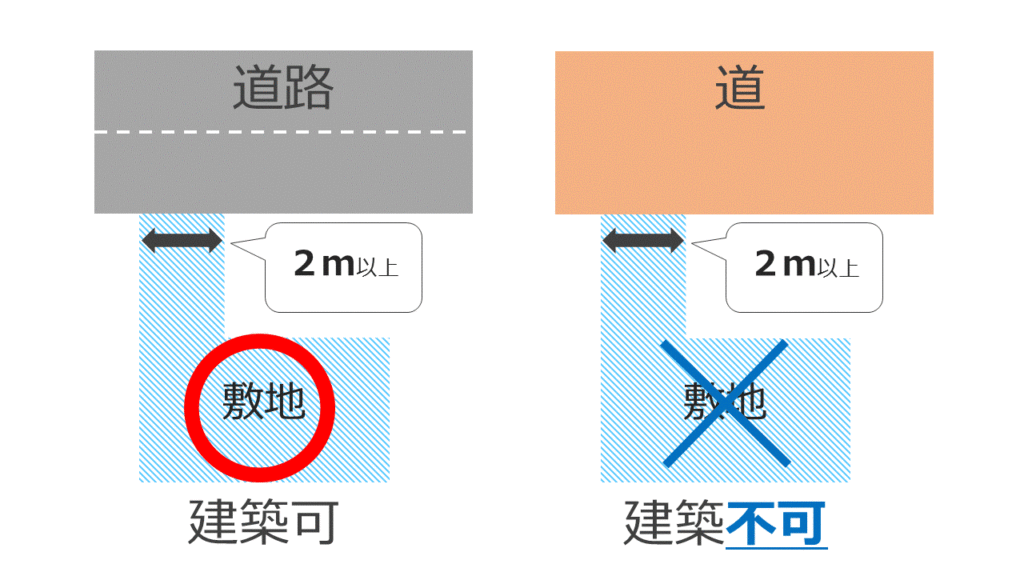
ただし、この接道義務が適用されないケースがあったのですが、それは以下の通りで、この条文は今も残っています。
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
こちらには建築審査会の同意を得て許可という文言が含まれています。
そして先ほどの条文に戻ってみましょう。
その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
建築審査会が登場しません。
文章だけではややこしいので、以下の図もご確認ください。
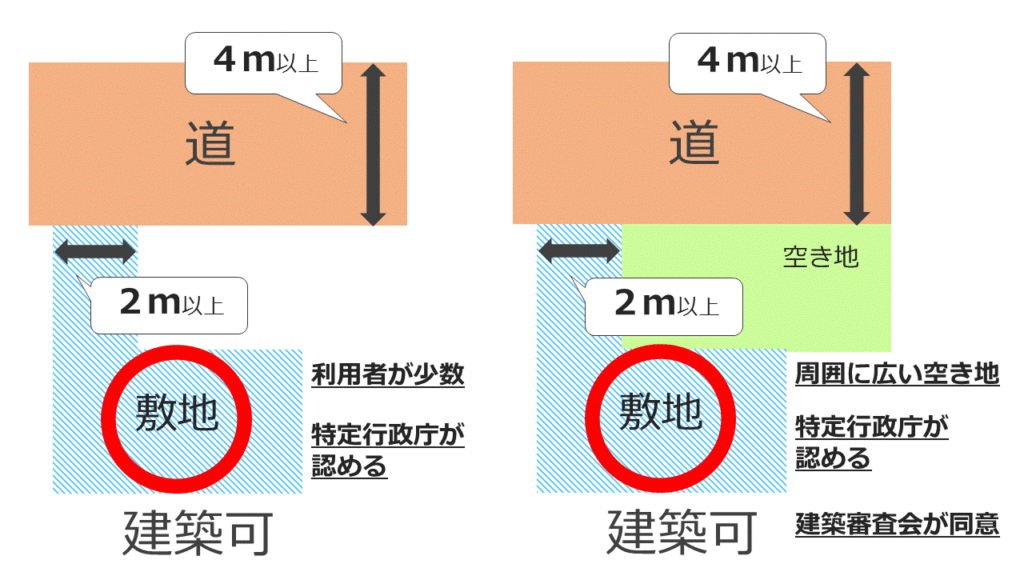
左側が新しく設定されたものであり、建築審査会が同意という内容がなくなっています。
接道は不動産にとって非常に重要ですので、改正された今年は狙われる可能性がありますので、しっかりと理解して本番に臨んでください。
改正点③
接道義務の付加
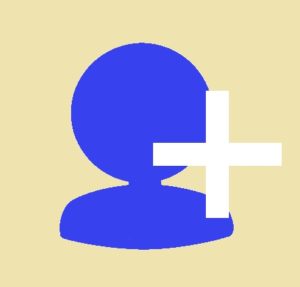
それでは次の問題です。
地方公共団体は、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
2019年の改正点を正確に把握されている方であれば、楽に解ける問題です。
さあ、いかがでしょうか?
正解は・・・
地方公共団体は、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
赤字の部分が間違っています。
袋路状敷地の接道義務の付加が可能に

地方公共団体は、一定の建築物について、条例で接道義務を付加できます。
地方公共団体は、次のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
そして改正により、以下の建築物についても接道義務を付加できるようになりました。
その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)
これも言葉だけではややこしいので、図でご紹介します。
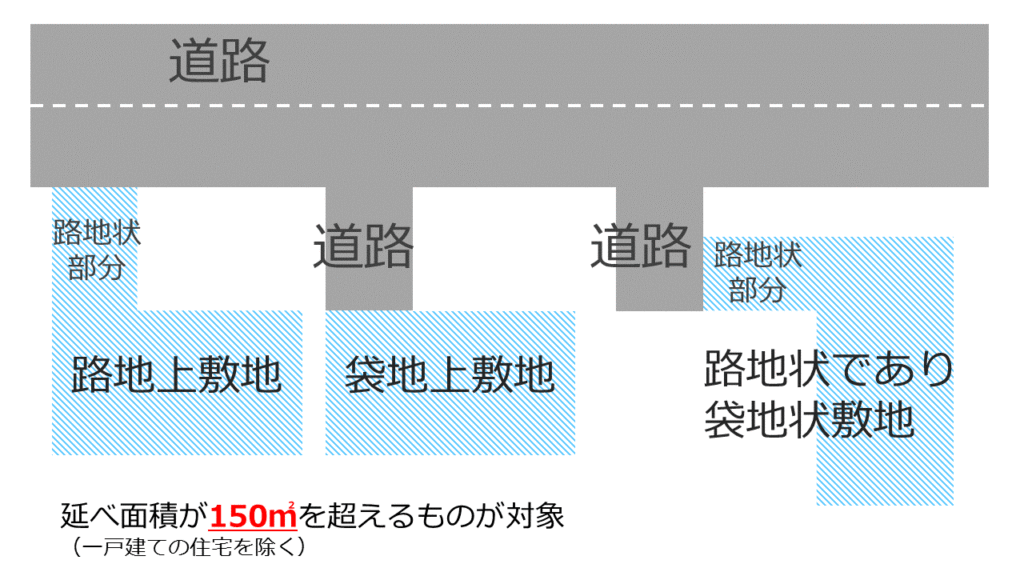
このような敷地にある150㎡の建築物に対しては接道義務を付加できるようになりました。
図で示した土地はその形から旗竿地と呼ばれていますが、これまではアパートは建築できなくても、重層長屋は建築する事ができる場合がありました。
簡単に言えば、この重層長屋の建築に対して規制ができるようにしたという事です(そのため一戸建てが除外されている)。
なお重層長屋とアパートの違いについては以下の資料が参考になりますので、ご確認ください。
延べ面積への不算入

次の問題文ですが何が間違っているか分かりますでしょうか?
老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分は、当該老人ホーム等の延べ面積の3分の1を限度として、当該老人ホームなどの延べ面積に算入しない。
2019年度の改正点を正確に把握されている方であれば、楽に解ける問題です。
さあ、いかがでしょうか?
正解は・・・
老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分は、当該老人ホーム等の延べ面積の3分の1を限度として、当該老人ホームなどの延べ面積に算入しない。
赤字の部分が間違っています。
老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積については、共同住宅と同様、容積率の算定上、建築物の延べ面積に算入しない。
3分の1を限度とするのではなく、全てが不算入です。
今回ご紹介した改正点は狙われる可能性が十分ありますので、勉強の参考にしていただければと思います。
今回もお読み頂きありがとうございました。
↓↓さしつかえなければ応援のクリックをお願い致します↓↓



